島﨑弁護士の「底地の気になるソコんとこ」
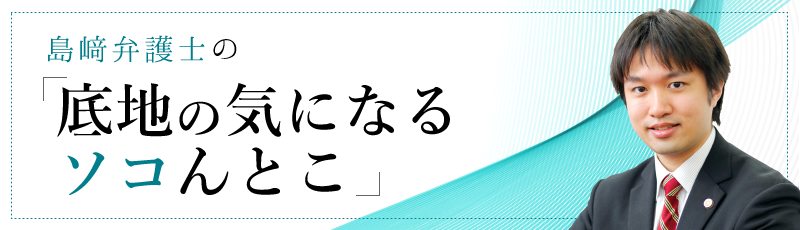
不動産の中でも、底地にまつわるトラブルは非常に多いです。
不動産に関する問題を多く取り扱う、半蔵門総合法律事務所の島﨑政虎弁護士に、実際に起きた事例や解決方法を紹介していただきます。
前回までは、使用貸借契約が賃貸借契約に変化してしまうという事例を紹介しました。
・使用貸借」に切り替えて、地主に有利な契約を結ぶことはできる?
今回は、借主が死亡しても、使用貸借契約が終了しなかった事例をご紹介します。(リビンマガジンBiz編集部)

(画像=写真AC)
<相談例>
地主「土地を無料で貸しています。もし借主がお亡くなりになった場合、土地は返してもらえるんですよね」
弁護士「原則はそうです。しかし、例外もあり注意が必要です。契約書は作っておいた方が良いですよ」
■おさらい:使用貸借とは
建物所有目的で借地人が一定の対価を支払い土地を使っている場合、旧借地法・借地借家法によって、借地人が非常に手厚く保護されています(賃貸借)。
一方で、土地利用者が土地利用の対価を払っていない場合は、土地の使用貸借となり、通常の借地と異なり、土地の利用者は保護されません。
<賃貸借と使用貸借の保護の程度の利用権の相続に関する違い>
|
|
賃貸借
|
使用貸借
|
|
利用権の相続
|
相続される
|
原則として相続されない
(民法599条)
|
建物所有目的の場合の例外
裁判所は、いくつかの事例で、借主が死亡してもその相続人が土地を使い続けることを認めました。
いずれも、契約書がない事例です。
2つの裁判例を紹介します。
<東京地裁昭和56年3月12日判決の事案>
昭和25年4月頃:
土地所有者AからCが土地を借りた。対価なし。契約書なし。
目的:居住用建物の所有。
昭和27年:
C、本件土地上に建物を建築し、所有。
昭和31年:
原告、Aから土地を取得。
昭和36年2月:
C死亡、妻D+子5人(E1〜E5)
昭和50年まで:
D病臥、E3が介護し、家族(夫・子)とともに同居。
昭和52年:
明渡請求。
裁判所は、建物所有目的であることを基礎として、貸主側に「死亡後も使わせる意思があった」と認めました。民法599条(「原則として相続されない」)が当然に適用されるものではないと判断しました。
<東京高裁平成12年7月19日判決の事案>
平成6年頃:
土地所有者Aが、C及びCの妻が同席する場で土地の使用を承諾。
対価なし。契約書なし。
平成7年9月:
C、土地上に建物を建築し、所有。
平成9年10月:
C死亡。
裁判所は、契約締結の場にC妻が同席していたこと、C妻が同居することを理由として、「C妻も使用貸借契約の借り主であった」と認め、Aの土地明渡し請求を排除しました。
両裁判例の総括
裁判所は、どちらも個別の事例から判断しています。
両事例に共通するポイントは、「契約書がない」ことによって、裁判官が契約の締結の時にあった様々な事情から、契約当時の当事者の意思を解釈している点です。
土地所有者が、契約の時に「死亡したら土地を返してもらおう」と思っていたとしても、契約書として残しておかないと、後から別の意思だったと判断されてしまう可能性があるのです。
まとめ
使用貸借契約は非常に不安定な権利です。
借地権に比べて保護が非常に薄く、相手を出て行かせやすいため、地主にとっては賃貸借契約より好都合なものとなります。
しかし、書面により合意していないと、後から合意の内容や終了の条件について紛争になる可能性があります。また、その際に地主から借地人にどのような説明をしたかについても、説明書面などで残しておくと、後から合意の有効性を争われづらいです。
特に、死亡により終了させたい場合は、その旨合意した書面が残っていないと、死亡後も使わせる意思があった、と裁判所が判断する可能性があります。
使用貸借契約と借主の死亡についての基本的な点については、以下のウェブサイトに詳しくまとめてあります。併せてご覧いただければ幸いです。
【借主の死亡による使用貸借の終了と相続(土地の使用貸借の特別扱い)】
https://www.mc-law.jp/fudousan/23991/
連載記事、島﨑弁護士の「底地の気になるソコんとこ」は、今回で終了します。ご愛読ありがとうございました。


